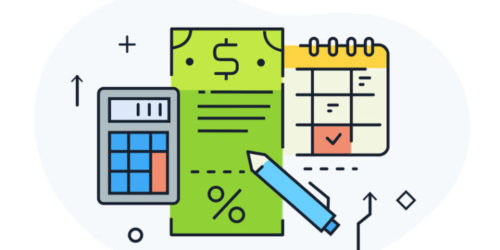- ふるさと納税とは、自治体に寄付することで所得税と住民税から控除を受けつつ自治体の特産品が受け取れる仕組み。
- ふるさと納税は個人事業主でも利用できる。
- 控除上限額があるため、事前に控除上限額を計算したうえでふるさと納税することが大切。
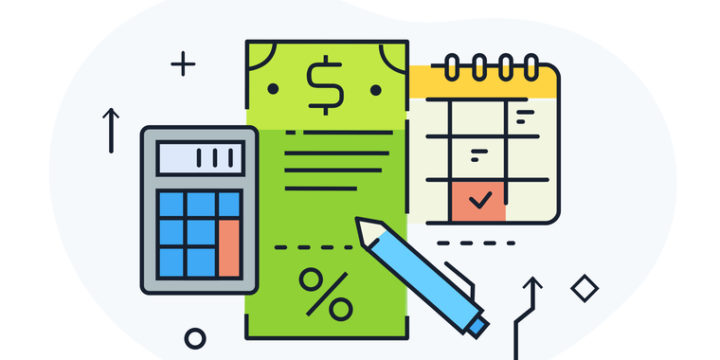
個人事業主はふるさと納税の上限金額に注意!流れ&計算方法をFPが徹底解説
公開日:2020年5月1日
この記事のポイント
選んだ自治体を応援しつつ、お得な特産品がもらえ、かつ大きな減税が受けられるとのことで「ふるさと納税」が人気を集めています。ただし、ふるさと納税で税金の控除を受けるには上限額があり、個人事業主の方はその計算方法に十分注意する必要があります。
本記事では、ふるさと納税の流れや控除上限額の計算方法などをお伝えしていきます。
ふるさと納税とは

ふるさと納税とは、全国の都道府県や市区町村に寄付することで、該当の都道府県や市区町村から返礼品を受け取ることができ、かつ寄付額に応じて所得税や住民税から還付を受けられる仕組みのことを指します。
過疎化の進む地方を応援するための取り組みとして2008年より始められたもので、地域の特産品を返礼品として得つつ、寄付額の大部分を所得税、住民税から還付してもらえるため年々人気が高まっています。寄付金控除はサラリーマンの方はもちろん、自営業の方でも問題なく利用できます。
なお、「ふるさと」と名前がつきますが、特に自分の生まれ育った地域でなくとも寄付することができますし、複数選ぶこともできます。
また、寄付したお金は教育や文化、産業、保険や医療、福祉など自治体ごとに設けられた項目を選ぶことができ、寄付したお金の使い道を指定できるようになっています。
ふるさと納税の金額や上限に関する計算方法

ふるさと納税では寄付額に応じて所得税や住民税から控除を受けられるようになっています。ここでは、その計算方法について見ていきたいと思います。
事業所得等の収入額の計算方法
ふるさと納税額の控除額を調べるにあたり、まずは事業所得や不動産所得、雑所得等、ご自分の事業で得た所得の額を算出するようにしましょう。
サラリーマンの方であれば、勤め先の会社が給与から源泉徴収してくれ、年末には源泉徴収票を発行してくれるのが一般的ですが、個人事業主の方は自分で所得を計算しなければなりません。
なお、事業所得、不動産所得、雑所得の計算方法は以下の通りです。
- 事業所得=総収入金額-必要経費
- 不動産所得=総収入金額-必要経費
- 雑所得=総収入金額-必要経費
いずれも、1年間で得た収入から1年間で支払った経費を差し引けばよいだけなので、考え方としてはシンプルです。なお、複数の項目で所得がある方はそれらの合計額を求める必要があります。
所得税の控除額の計算式
1年間の所得額を求めたら、ふるさと納税による所得税の控除額を求めてみましょう。ふるさと納税による所得税の控除額は以下の通りです。
- ふるさと納税による所得税の控除額=(寄付金額-2,000円)×所得税の税率
ここで、所得税の税率は所得額が高くなるほど税率の高くなる累進課税制度となっており、先ほど求めた所得額の合計により、以下のように税率が変わります。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
例えば、所得額300万円の方が2万円ふるさと納税した場合の控除額をシミュレーションしてみると以下のようになります。
- 20,000円-2,000円×10%=1,800円
住民税の控除額の計算式
次に住民税の控除額の計算式を見てみましょう。住民税の控除額の計算式は以下の通りです。
- ふるさと納税による住民税の控除額=基礎控除額+特例控除額(AorB)
- 基礎控除額=(寄付金額-2,000円)×10%
- 特例控除額(A)=(寄付金額-2,000円)×(100%-10%-所得税の税率)
- 特例控除額(B)=住民税所得割額×20%
※Aの計算結果がBを超えるときにBとなる
例えば、先ほどと同様2万円寄付した場合で見ると、以下のように計算できます(ここでは特例控除額(A)で計算します)。
- 基礎控除額:(20,000円-2,000円)×10%=1,800円
- 特例控除額(A):(20,000円-2,000円)×(100%-10%-10%)=14,400円
- 合計:1,800円+14,400円=16,200円
ふるさと納税には控除上限額がある
上記、所得税と住民税の控除額を計算してみると、所得税の控除額1,800円と住民税の控除額16,200円ですから、合計18,000円と、実質負担額2,000円で返礼品がもらえる計算となっています。
しかし、ふるさと納税には控除上限額があり、上限を超えてふるさと納税してしまうと超えた分について還付を受けることができず、自己負担額が大きくなってしまいます。このため、あらかじめ控除上限額を調べておき、ふるさと納税額が上限額以下になるよう計算しておくことが大切です。
なお、個人事業主の方のふるさと納税額上限額の目安は、「住民税所得割額の2割程度」となっています。住民税所得割額は住民税の納付書(住民税決定通知書)で確認できます。やや複雑ですが、以下の計算式を使うと正しい寄付可能上限額を求められます。
- {(住民税所得割額×20%)÷{90%-(所得税率×1.021)÷100}}+2,000円
ふるさと納税の流れ

ふるさと納税をするときは以下のような流れで手続きを進めましょう。
- ふるさと納税したい自治体を選ぶ
- 寄付金を納付する
- 確定申告する
それぞれについて詳しく解説します。
ふるさと納税したい自治体を選ぶ
まずはふるさと納税したい自治体を選びます。自治体ごとに設けられた、返礼品や寄付金の使い方などが書かれたサイトを見て選ぶとよいでしょう。ふるさと納税する自治体が決まったら、サイト内にあるふるさと納税の申込みフォームから申込みを行います。
寄付金を納付する
ふるさと納税の申込みが終わったら自治体に指定された方法で寄付金を納付しましょう。
自治体が寄付金の納付を確認すると、返礼品と共に「寄付金受領証明書」が送られてきます。寄付金受領証明書は確定申告の際に必要となるので、万が一送られてきていない場合には自治体に問い合わせするとよいでしょう。
確定申告する
ふるさと納税を行った年の翌年2月16日~3月15日の間に行う所得税の確定申告で、ふるさと納税について申告します。
本記事中で解説している通り、個人事業主の方はその事業で得られた所得を事業所得や不動産所得、雑所得などとして計算します。それと同時に、ふるさと納税で寄付した額を記載することで、所得額から控除されるという仕組みです。
サラリーマンの方や、個人事業主の方でも下請けの場合で取引先が源泉徴収している場合には、控除した結果、所得税を納め過ぎていた場合には差額が還付されることになります。
一方、源泉徴収されていない場合には、ふるさと納税で控除を受けた分だけ、納付する所得税の額を少なくすることができます。
なお、個人事業主の場合、税務署に対して事前に届出を出し、複式簿記による方法で帳簿をつけるなど一定の条件を満たすことで青色申告することができますが、ふるさと納税による控除は、基本的に青色申告の場合でも白色申告の場合でも同様の手続きで行います。
住民税の控除
ふるさと納税では、所得税だけでなく住民税からも控除を受けることができます。住民税の納付額や控除額については、所得税の確定申告をすることで、その申告額を基に自動で住民税の納付額が計算される仕組みになっています。
通常、1月~12月の1年間の所得を翌年2月16日~3月15日の間に確定申告し、その年の6月頃より自治体から送付される納付書で住民税を納付します。
個人事業主のふるさと納税に関するまとめ
個人事業主のふるさと納税について、控除額の計算方法や流れについて解説しました。ふるさと納税は節税効果が高く、実質負担額2,000円で自治体の特産品が返礼品としてもらえるなど非常にお得な制度です。
一方、ふるさと納税には控除上限額があるため、あらかじめ控除上限額を調べたうえで実施することが大切だといえます。
個人事業主におすすめ!便利な確定申告サービス
領収書の管理~確定申告までスマホで完結できるクラウド会計サービス「freee」を使うと簡単に確定申告できます。
確定申告のやり方がわかない方も心配ありません。ステップに沿って質問に答えるだけで確定申告書類を作成してくれます。